ジョギングでもパワー計測ができる(ガーミンランニングダイナミクスポッド)
自転車業界において最初のパワーメーターが登場したのは1987年だそうです。SRM社が1986年に最初のパワーメーターを開発し、翌年に特許が公開。
当時はスパイダーアーム式クランク用のパワーメーターだったそうですね。
自転車におけるパワーメーターはかれこれ30年近い歴史があるわけですね。
かくいう私も、一昨年にパワーメーターを導入し、かれこれ2年近く使ってきました。
レースに出るわけでもない週末ローディーなわけですが、パワーメーターで取得できるデータは面白いものがあって、とても満足しています。
当時は海外から個人輸入で購入したコスパ最強の4iiiパワーメーターですが、今では国内でも取り扱いが開始していますので、Amazonでもお手頃価格で購入できるようになりましたね。
で、昨年から始めたジョギング生活。
ランニング界隈でもパワーメーター的なものってあるのかな?と調べてみるとあるじゃないですか。
今回はランニング用のパワーメーターに関するお話となります。
1. まだ日が浅いランニング用パワーメーター
自転車においてはパワーメーターは歴史のあるツールとなりますが、ランニング業界においてはまだ日が浅いようです。
Strydが胸に巻くベルトタイプで2015年にクラウドファンディングで募集を行ったのが最初だそうで。
そのせいか、自転車用のパワーメーターと比較すると巷にもまだ情報が豊富ではないようです。
2. ランニング用パワーメーターの種類
ランニング用のパワーメーターは探せば色々とあるようなのですが、比較的購入し易い有名どころはこの辺りでしょうか。
Stryd
ランニング用パワーメーターのパイオニア、Strydです。定価は199ドルだそうですが、公式サイトから送料込みで購入すると 32,000円だそうで。
ま、ロードバイクのパワーメーターからすると「まだお安いじゃない」と思えるのですが、まだジョギング初めて日も浅い人間からすると、いきなりそこまで飛び込むには勇気が入りますね。

ちなみにこちらはシューレースに取り付けるタイプだそうです。
使い続けているとそこそこ汚れそうですね。
ガーミンランニングダイナミクスポッド

ガーミンでもないかな?と調べたらありましたねー。
ランニングダイナミクスポッドと呼ぶそうです。アクセサリー扱いになるので、公式サイトでもひっそりと存在感があまりありません。
低下が税別で8400円。これはパワーメーターとして考えると破格ですね。
ということで、迷わずお買い上げ。
3. ガーミン ランニングダイナミクスポッドを購入

なんでしょうね。
普通に考えるとそんなにお安い買い物ではないのですが、自転車用のパワーメーターに慣れた目からすると、一万円切っているだけで感激ものでした。

大きさは本当に小さくて「これで大丈夫なの?」と心配になってしまいます。
取り付ける場所は腰の辺り。

後ろのこのフック部分をズボンなどに引っ掛ける形になります。

こちらマニュアルから拝借。
ペアリングですが、1度ペアリングに成功してしまえば、以降は ForeAthlete 745でランニングのアクティビティが開始すれば自動的に接続してくれます。
また、ジョギング終了後は「忘れずに外してね」という通知もガーミンスマートウォッチの画面に表示されます。
ただ、表示されてから自宅にたどり着き、洋服に着替える頃にはすっかり失念していることもあり、何度か洗濯機に入れたまま洗濯しそうになりました・・・汗
ちなみに「あるある」なんでしょうね、マニュアルにも注意書きがありました。
洗濯機の使用はお避けください。万が一洗濯機で洗ってしまった 場合でも低温から中温の水であれば耐えうる設計ですが、温水 での洗濯や乾燥機の使用、冷水であっても繰り返し洗濯してしま うと故障の原因となります。
気をつけないとです。
4. ランニング用パワーメーターで取得できるデータ
ガーミンランニングダイナミクスポッドで取得できるデータは以下となります。
結構多いです。
実は購入から既に2ヶ月程度経過しており数十回使用しておりますので、自分のデータとも比較していきたいと思います。
(1) 接地時間
読んで字の如く、地面に足が着いている時間ですね。
ガーミン公式の説明によるとこんな感じだそうです。
- 一流ランナーほど設置時間は短く、多くの一流ランナーは200ms未満
- 経験豊富なランナーになると、ほぼ全ての人が300ms以下
設地時間はストライドと関連性があるようです。
ストライドが自分の適正範囲よりも大きくなっている場合(オーバーストライド)、足が上体よりも前方に着地してしまう為、着いた足に体を引き寄せてから足を離すまで長い時間がかかることとなり、結果として設地時間が長くなってしまうそうです。
このオーバーストライドの状態は、走りにブレーキがかかることが多いそうであまり好ましくないようで。
では自分はどうか、ドキドキのデータ比較です。
左側の数値が「奥様と一緒にのんびり走っている時」でして、右側がこの2ヶ月で最も早いタイムを記録した時のデータとなります。
平均設地時間 (278ms / 267ms)
お?
いちおう経験豊富なランナーと認定されました・笑
(2) GCTバランス
GCTバランスは、左右の足の設置時間のバランスのことですね。
自転車用のパワーメーターでも左右のバランスとか出ますよね。
(私の場合は片足用のパワーメーターなので、常に左が100%ですが・・・)
基本的には左右がより対照的なフォームが望ましいようです。
こちらの値はリアルタイムで確認することも可能でして、疲労している状態や坂の登り下りの時に左右のバランスが崩れることが多いそうです。
バランスが崩れると怪我をするリスクにもつながりますので要注意ですね。
ま、左右バランスをウォッチフェイスで確認しながら走るほうがよっぽど転んで怪我しそうですが・汗
平均GCTバランス (49.4%左・50.6%右 / 49.6%左・50.4%右)
のんびり走っている時よりも、頑張って走っている時の方がバランスは良さそうですね。なんでだろ。
私は聞き足が右になりますので、右側の比率が高くなっているようですが、そこまで神経質になるほどの偏りはなさそうです。
(3) ピッチ
1分あたりの両足の合計歩数になります。
自転車でいうケイデンスですね。
あちらは1分あたりの回転数ですが、ピッチは両足の合計歩数になりますから感覚的にはケイデンスを倍にしたものがピッチ、と考えるとしっくりきそうです。
ただ、ランニングにおけるピッチはフォームの適正さにも関係しているそうで。
所定のペースでピッチが速くストライドが短いと、体の多くの場所にかかる負荷が小さくなるそうです。
「適正なピッチとストライドをキープすることが、足首、膝にかかる負荷が少ない優しい走り方になる」というのは、なるほど納得です。
よく引き合いに出されるピッチは「180ピッチ/分」だそうです。
これって、ロードバイクでもよく言われる「ケイデンス90」に通じるものがありますね。
で、私のピッチはこちら。
平均ピッチ (174ms / 165ms)
早いタイムの方がピッチが遅いですね。
これは体感とも一致してまして、奥様とゆるゆる走る時には小さな歩幅で走っている為、結果的にピッチが高くなっているようです。
ただ、頑張って走っている時のピッチが低い点については、今後改善すべきなのかは、何度か走り方を変えながら自分なりに突き詰めていく必要がありそうですね。
ちなみにロードバイクでも私ケイデンスは低いほうでして、ライド後の平均ケイデンスが80を超えることはあまり多くありません。
普段走っている時には85rpm辺りが個人的に快適なゾーンだったりしますので、もし同じような考え方が通用するなら、ランニングにおいても170msあたりが私の快適なゾーンなのかもしれません。
(4) ストライド幅
ストライド幅は、左右のステップで進んだ距離の長さになります。
さすがに「このストライド幅が適正ですよ」という数字はなさそうです。
走り方にも「ピッチ走法」「ストライド走法」とあるように、どちらかが正解、というものはないようですね。
こちらが私のデータ。
平均ストライド幅 (0.75m / 1.07m)
こちらも納得です。
ゆっくり走っている時はピッチ走法、一人で頑張って走っている時はストライド走法になっているわけですね。
ストライドが大きくなると速くはなるのでしょうが、怪我のリスクも高まりますので、私のようなファンランナーがいきなりストライド幅をぐいぐい上げていくような走り方はしない方が良いそうです。
徐々に、ですね。
(5) 上下動
上下動は、ランニング中のステップによって体がどれだけ上下に動いたかを示してくれるものとなります。
要はどれだけ「弾んでいるか」ですね。
一般的には、上下動は少ない方が余計なエネルギー消費がないので経済的と考えられているようです。ガーミンの研究結果によると、経験豊富なランナーほど上下動は低く、経験の浅いランナーは上下動が大きくなり余計なエネルギー消費につながってしまうそうです。
平均上下動 (7.5cm / 9.6cm)
自分のデータを見るとよく分かりますが、頑張って走っている時にはゆったり走っている時よりも明らかに上下に弾んでいますね。
これは経年とともにどれだけ小さくできるのか、今後要注目です。
(6) 上下動比
上下動比は、各ストライドで前進した距離と上下動との比率になります。
計算式は単純で、各ストライドにおける上下の弾み量をストライド幅で割ったものとなります。
これまで書いてきた内容からもピンと来るかと思いますが、上下動比が低いほどより少ないコストで前進できていることになります。
平均上下動比 (9.9% / 8.8%)
おお。
奥様とゆったり走っている時は、あまり効率的な走りができていない、ということですね。
ある程度スピードを抑えながら走っていますのでそこは仕方ないとしても、もっと余計な上下動がない省エネな走り方を身につけた方が良さそうです。
(7) ランニングパワー
こちらがメインイベントでしょうか。
何はなくともパワー、です。
Garminラボで開発されたRunning Powerアプリでは、ペースや上下動、傾斜、その地域の風の状況などの測定基準を基にして、ランニング時に地面にかかるパワーが計算されます。どのくらいのパワーを分単位、およびマイル単位で使っているのかを把握することで、自分のペースを向上させ、すぐに疲れることのないようにすることができます。
あなたの体のエネルギーを、スマートフォンのバッテリーだと考えてください。画面を常に明るくすることはできますが、その結果、バッテリーの消耗も激しくなります。一方で、画面を暗くすることで消費を節約し、バッテリーを長持ちさせることもできます。これと同様に、あなたの体について知り、様々な状況下でのランニング時に発揮されるパワーを理解することで、このデータをモニタリングして、エネルギーを節約することが可能なのです。マラソンやその他の長距離ランをする場合に、トレーニングとレース当日のパフォーマンスの微調整に役立ちます。
自転車におけるパワーメーターは「ひずみ」をもとにダイレクトに算出されますが、ランニングにおいてはかなり複雑な計算が必要なようですね。
そして、私も最初に使った時に驚いたのですが、ランニングにおいては自転車の時よりもパワーは「大きく」なります。
ランナーの多くは、ランニングパワーが自転車のパワーよりもはるかに高いことに驚かされます。実際、ランニングパワーは自転車パワーよりも高くなるとされ、これはサイクリング(約20-25%)よりもランニング(約40-45%)の方が代謝効率が高いことに起因します。つまり、サイクリング時よりもランニング時に、アスリートは同量の酸素をより多くのパワーに変換できるというわけです。あるいは心拍数に言及した場合、同じ心拍数でより多くのパワーを出すことができることになります。これは主に、ランニングの場合、腱などの弾性要素の受動的反動のメリットがあることによります。わかりやすく言えば、地面に足を付ける時にはエネルギーが蓄えられ、足を上げた時にエネルギーが戻るのです。これはサイクリングには当てはまりません。
より大きなパワーに変換できる、とはポジティブな表現ですが、裏を返すと「より大きなパワーがないと推進力に変えられない」ということでもあります。
自転車は生み出したパワーを推進力に「より効率的に」変換できる乗り物ですからね。
平均パワー (184.0W / 254.0W)
はい。
のんびりジョギングでもこのパワーですから最初は驚きました。
頑張って走った時のパワーを見た時に、「ロードバイクでこのパワーがあれば・・・」なんて思ってしまいましたねー。
ちなみに、いずれも小1時間走った時の平均パワーになります。
パワーメーターがあるということは、FTP計測もできるということですね。
ランニングにおいてFTPを計測する代表的な方法はこちら。
- 1時間走 1時間の全力走の平均パワーを算出する
- 20分走 20分の全力走の平均パワー×95%を算出
- 3分-9分走 ( 全力走3分の平均パワー + 全力走9分の平均パワー )÷ 2 × 0.9
最初の二つについては自転車と同じ考え方ですね。
ただ、正直限界まで追い込んだ60分走とか20分走なんて、想像もつきません・・・。
そこで現実的な可能性のあるものが3つ目の計測方法なのですが、こちらはTraining Peaks で紹介されているやり方になります。
全力走3分と9分についての計測ステップは以下だそうです。
- 5分のウォームアップ
- 全力走3分
- 徒歩5分→ジョグ10分→徒歩5分→ジョグ5分→徒歩5分(リカバリー期間)
- 全力走9分
- クールダウン10〜15分
全力走3分なら何とかイメージできますが、9分ですか・・・。人生において9分も全力疾走した記憶はありません・・・。
また、近くに計測に適したトラックがあるわけではありませんので、自転車以上に計測には困難が予想されますね。
多摩川の土手、平日の朝とかであればできるのかな?
体力的な問題以上にランニングではFTP計測は難しそうな気がしますが、いつかチャレンジしてみたいところですね。
いずれにしても面白いガジェットを購入しましたので、今後もランニングのパワーと自転車のパワーなど、色々と比較しながら楽しんでいきたいと思います。











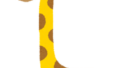

コメント
Garminのランニングダイナミクスは2014年以前からFR620などで計測出来ていましたよ。心拍センサーと一体型がメインで、あとはフットボッドやストライドセンサーで拡張データを取得していました。
更にはその前には、今は撤退しましたがAdidasがmiCoachシリーズとしてセンサーを腰に付けたりインソールに組み込んだり、果てはサッカーボールにまで付けたりで、各種データをチーム単位で解析なんてのもありました。私がAdidasから貰ったランニングシューズにもそれ用の穴があったのでセンサー買って付けたことがあります。
そのようなわけで、10年以上前からランでも心拍以外の各種センサーあって、ランのピッチはダッシュなら230spmとか上下動と接地時間を小さくするフォームとか走行会やSNSで情報飛び交ってましたよ。
ランニングダイナミクスはそうですよね。
パワーメーターとしてはstrydが初なのでは、という解釈が多いようです。
たふぁ、そこに至るまでは色々な試みがあったわけですね。